当サイトのリンクには広告が含まれています。

こんにちは、元緘黙の俊太です。
僕が緘黙のことを知ってから20年くらいたちました。
その間にいろいろ緘黙に関する本が発売されています。
今回紹介するのはこの本です。
| 場面緘黙支援入門 幼稚園や学校で話せない子どものための [ 園山 繁樹 ] 価格:1,760円(税込、送料無料) (2025/6/3時点) 楽天で購入 |
2025年現在日本で発売された最新の緘黙の本になります。
この本はスモールステップに関してどの緘黙の本よりも詳しく解説しています。
この本の内容を要約すると、緘黙の説明。
学校の先生が緘黙の子に気づいて親に連絡をする。
親と協力して緘黙の子が話せるようにする。
そのためにまずは教師が緘黙の子と信頼関係を築いて、スモールステップで緘黙を治していく。
という内容です。
この記事ではこの本の感想を書いていきます。
できたら本を読みながら読んでください。
内容に関してはこちらのYouTubeで解説している人がいるのでこちらも参考にしてください。
学校の先生がこの本を読んだらどうなるか?
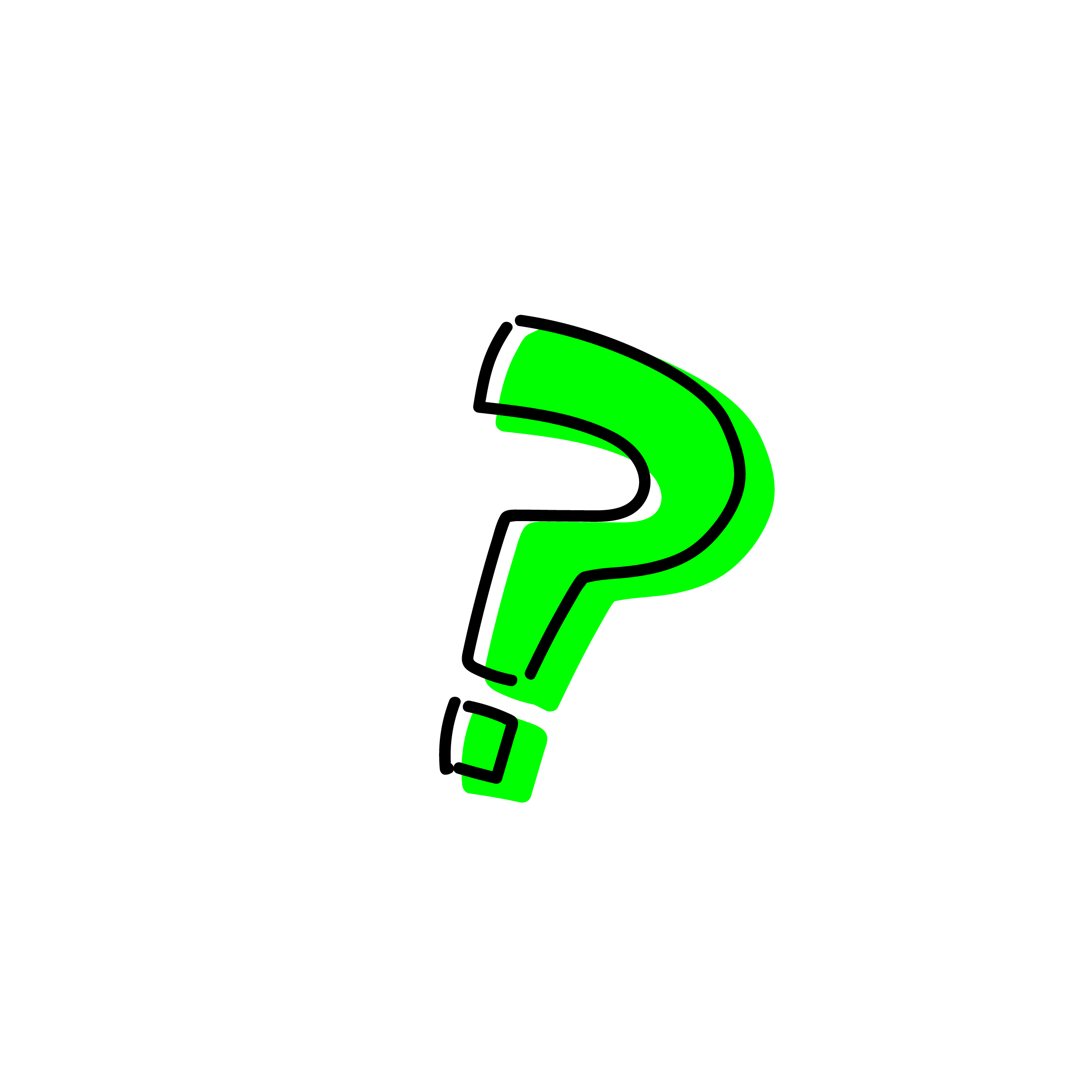
この本を読んで思うのはこの本に書いてあることを実践するのはかなり面倒だなって言うのが個人的な感想です。
たしかに教師がこれを実践したら効果はあると思うのですが、教師にしてみたら面倒なんですよね。
学校の先生にしてみたら緘黙の子を助けるメリットって何もないわけですから、この本を読んだ教師でこの本に書いてあることを完璧とは言わなくても大筋でも実践しようという人はかなり少ないと思います。
もし親が「この本に書いてあることを実践してください」と言ったらどうなるか?
遠回しに断られる可能性が高いかなって思いますね。
あるいは負担にならない範囲内なら実践してくれるかもしれません。
校長の命令だったらある程度は実践してくれるかもしれませんが、どの先生でも実践できるかどうかは微妙なところです。
親に緘黙のことを伝える
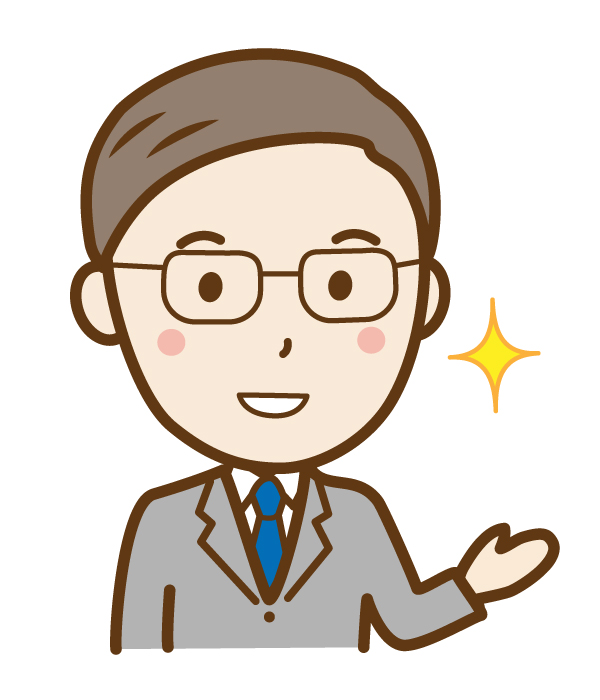
22ページを読んでください。
「緘黙は学校で主に発生するので親より教師が先に気づきます。そこで教師が緘黙に気づいたら親に家で話しているか確かめましょう。」
学校の先生がこの本を読んで実際に自分のクラスに緘黙の子を見つけたらこの本に書いてあるように親に緘黙のことを伝えるでしょうか?
僕としては微妙かなって思いますね。
親に緘黙のことを伝えるって結構リスクがあるんですよね。
親に伝えると「家の子はおかしくない」とクレームをもらうこともあります。
だから緘黙だと気づいても伝えない教師も多いような気がします。
伝えるにしても緘黙だと気づいてわざわざ伝えると言うより家庭訪問とかあった時に話の流れでやんわりと伝えるのが現実的な対応かなって思います。
緘黙の子の実態を把握する
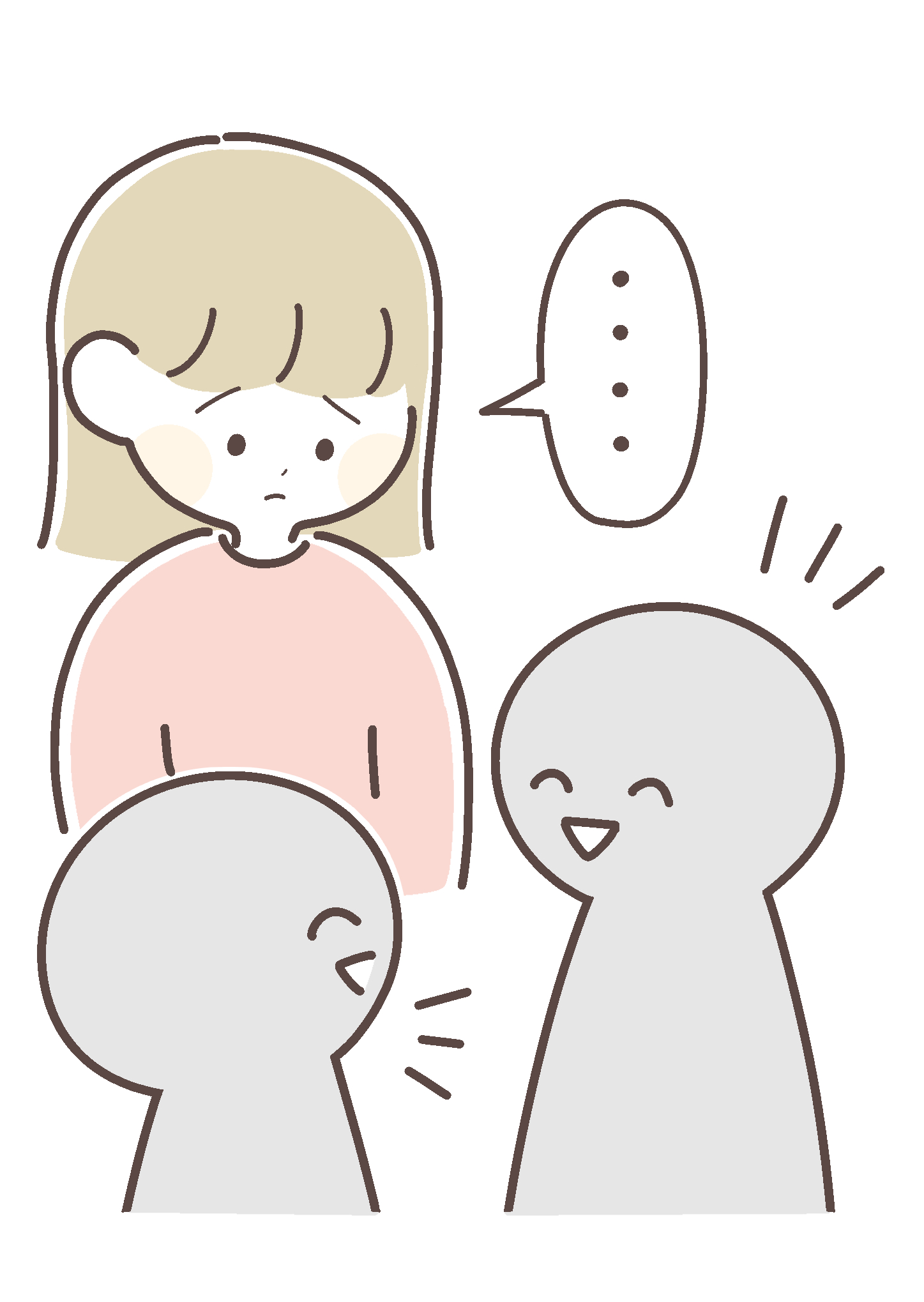
64ページを読んでください。
「緘黙の子の実態を把握する。」
「「場所」「人」「活動」の3つの組み合わせで何ができるのか把握する」
これを教師が把握するのって正直言ってかなり面倒な作業だと思います。
これを自ら進んでやるかどうか聞かれたら難しいかなって思います。
ただし緘黙の子の実態を把握するには教師である必要はありません。
ここに関しては教師ではなく親が作成することも可能です。
実態把握の資料に関しては、かんもくネットからダウンロード可能です。
子供と良好な関係を作る

92ページを読んでください。
「子供と良好な関係を作るために以下のことをする。」
- 返答を必要としない声掛けをする。
- 用事を頼んで褒める機会を増やす。
- 授業では指名しないから答えがわかったら手を上げるように約束をする
- 居残り学習の機会を作る
- 外遊びの宿題を出して特定の子供を自宅に迎えに行かせる
これは実践可能なのかと言うと「返事を必要としない声掛け」と「用事を頼んで褒める機会を増やす」のはやる気がある先生だったら可能だと思います。
指名をしないから手を上げるという約束もまあ可能だと思います。
居残り学習の機会や外遊びの宿題に関しては微妙なところですね。
ちょっと面倒だなって思う先生が多いと思います。
実践したら良好な関係を作るのに効果があるかと言うと効果があると思います。
ただ普段の人間性が大きく関わってきます。普段性格が悪い人が実践しても良好な関係を作るのは難しいと思います。
性格の悪い人は別としてまあごく一般的な先生の場合はどうかと言うと、ある程度の効果はあると思いますがこれを実践すれば必ず信頼関係を築けると言うほどではないかなって思いますね。
やはり普段の態度も重要になってきます。
合理的配慮
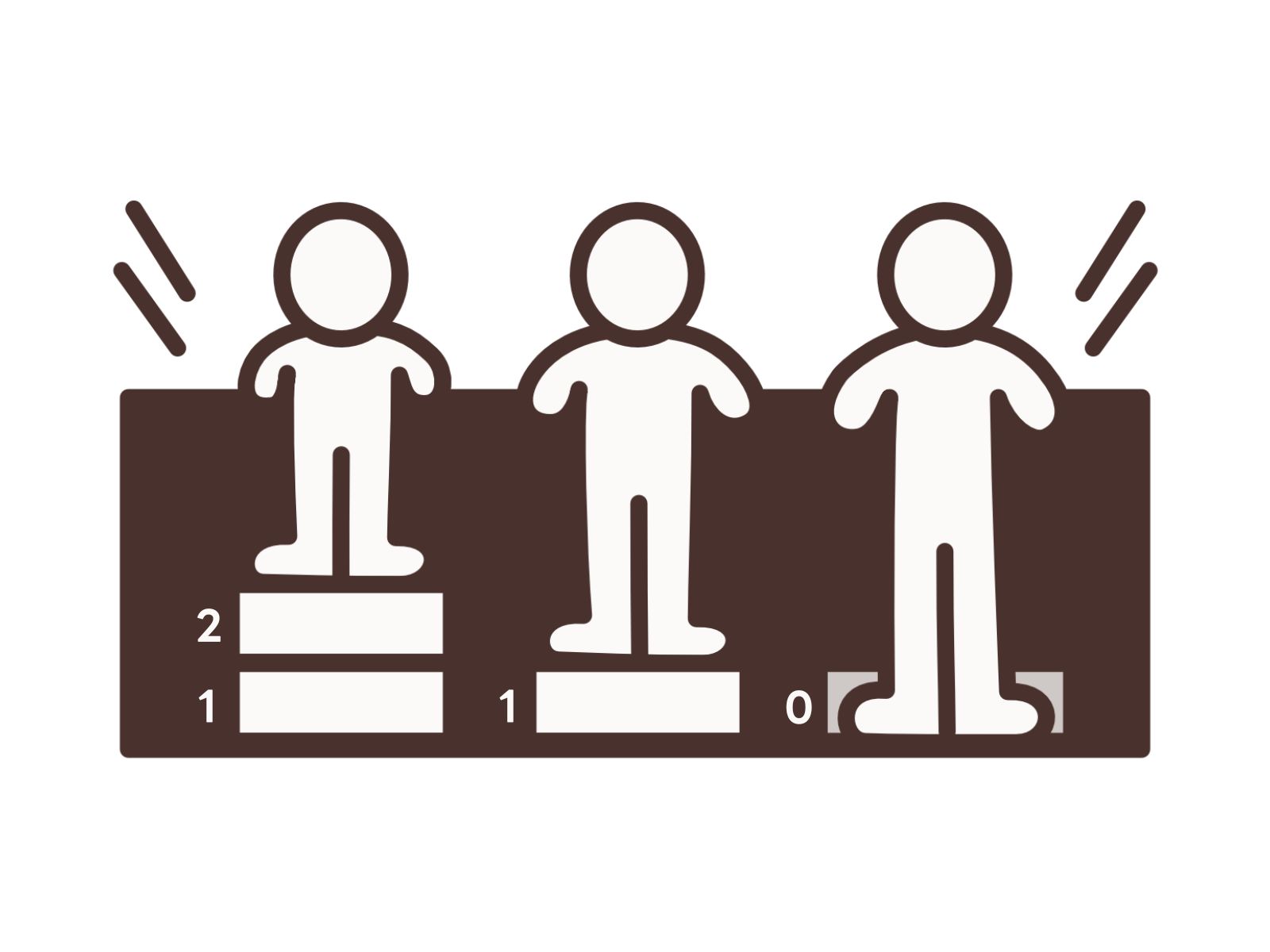
96ページを読んでください。
- 朝の健康観察で声の返事以外で答える
- 集団で本読みをする
- グループでの歌唱
- 口パク
- 代読
- 板書
- 筆記や便利器具
- 選択肢を出す
これらに関しては親が学校の先生と協議して決める必要があります。
あとは子供の気持ちの確認も大事です。
そして学校がどこまで対応してくれるかですね。
「朝の健康観察で声の返事以外で答える」に関しては対応可能だと思います。
「集団で本読みをする」に関してはどうかなって思います。
学校としては手間がかかって面倒と感じるかもしれません。
無理なら普通にパスを認めてくれれば問題ないかなって思います。
「グループでの歌唱」歌ってたいていは1人ではなくみんなで歌うからこの辺は問題ないかなって思います。
ただし成績をつけるときに一人で歌うのは避けられません。
この場合は成績はつかなくていいからパスを認めてもらいましょう。
「口パク」口パクで意思をくみ取ってくださいってかなり難しいと思います。
「代読」隣の子に答えを答えてもらう。まあギリギリOKかなって思います。この辺は学校の先生の判断ですね。
「板書」答えを黒板に書く方法ですが、他の子を巻き込むのは微妙なところですね。
「筆記や便利器具」電子メモ帳を利用する方法です。この辺は学校の先生の判断が別れると思います。
「選択肢を出す」答えをいくつか提示して手を挙げてもらう方法。これも他の子を巻き込むので微妙なところです。
スモールスモールスモールステップ
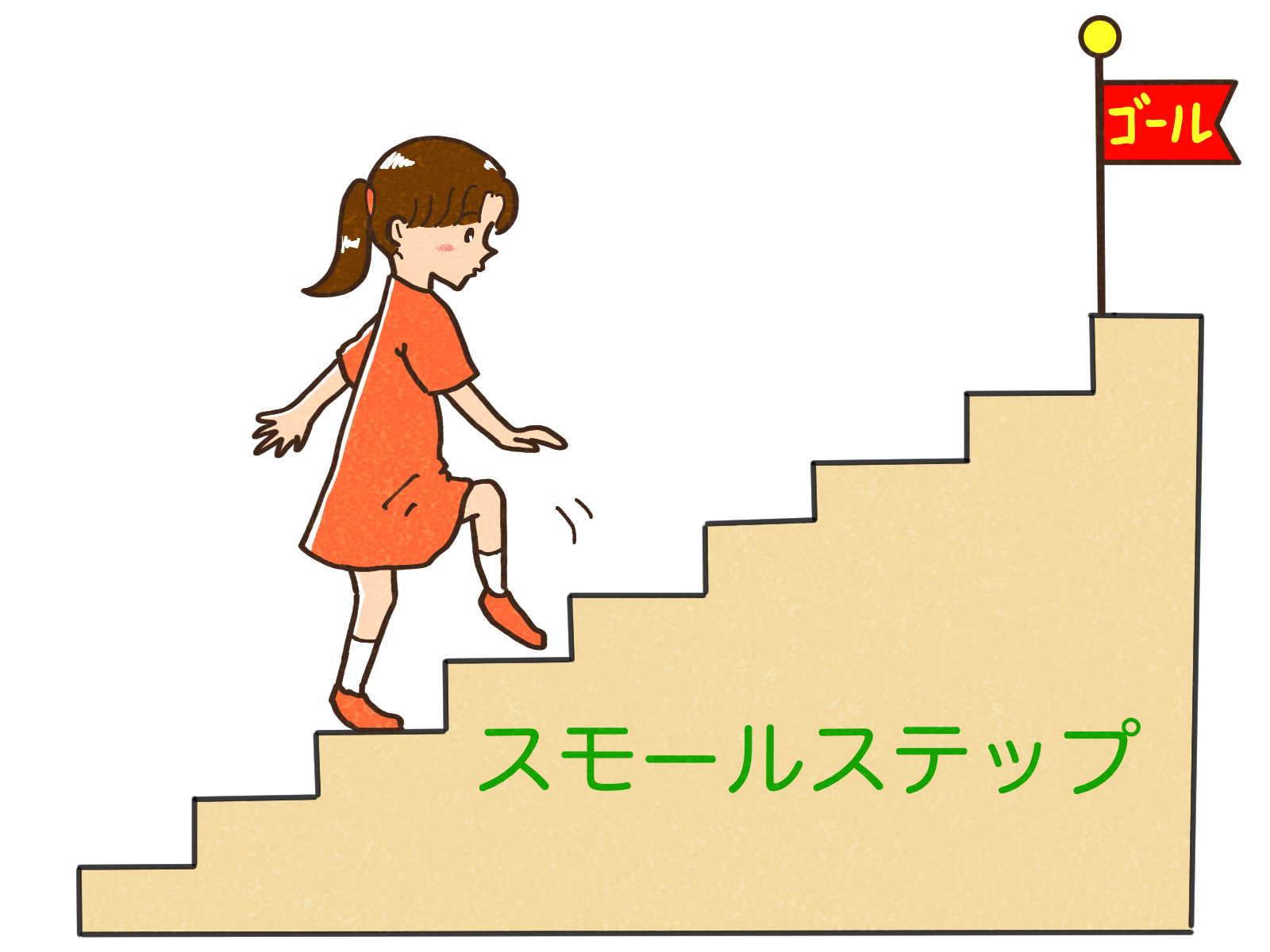
120ページを読んでください。
緘黙の子は学校で同級生とは話せない。
緘黙の子は家で親とは普通に話せる。
では緘黙の子は学校で親と二人きりで話せるのか?
学校で親と二人きりで話せるならそこに学校の先生がちょっとだけ覗く。
それでも話せるならほんのちょっとずつ学校の先生が入っていく。
小さなステップをちょっとずつ登って行って最終的には学校で話せるようになる方法です。
この方法は学校の先生や同級生の協力が必要になります。
学校の先生に頼んだら協力してくれるかどうかは微妙なところですね。
それに1回だけやればすぐに話せるようになるわけではありません。
親の側も何度も学校に行くことになりかなり負担になります。
成果が出ればまあそのくらいの負担は良いと思いますが、思うように改善しないこともあるのでなかなか難しいところですね。
本に書いてあることを実践したら緘黙は治るか?

本を読んだら実践するかどうかは別としてもし学校の先生がこの本に書いてあることを実践したら効果はあると思います。
ただ確実にすべての子に効果があるかと聞かれたらちょっと難しいと思いますね。
緘黙の程度が重いと実践しても結果が出るかどうかは微妙です。
でもほとんどの緘黙の子は実践すれば必ず話せるようになるとは言いませんが、ある程度の効果はあると思います。
自分の子供の頃にこの本があったらどうなるか?

僕が子供の頃は当然緘黙の本なんてなかったのですが、もし子供時代にこの本があって各学年の担任の教師が読んでいたらどうなったでしょうか?
多分本を読んでも実践した教師は1人もいないと思いますね。
でも親が頼んだ場合や校長が命令した場合はどうなったか?
ある程度は実践してくれたかもしれませんが、正直効果があったかどうかは微妙ですね。
ではもしすごく良い先生が実践してくれたらどうなったでしょうか?
この場合は結構効果があるかもしれません。いじめに関してはこの本はさらっと書いてあるだけですが、熱心な先生だったらそもそもクラスでいじめが起きないと思います。
気になったこと
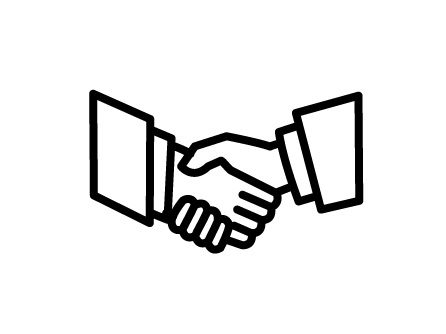
この本にはこんなことが書いてあります。
「専門家と学校の先生が連携する」
「専門家の連携協力が得られれば先生も心強いし自信をもって取り組むことができるでしょう」
そうでしょうか?僕はそうは思わないんですけどね。
この本を書いた人に限らずですが学校の先生が緘黙の子を助けたくて治したい。
そう考えていると思っているようですが、教師にしてみたら緘黙の子が話せるようになっても何の利益にもならないわけです。
負担にならない範囲なら協力してもいいけど、あれやこれやと指図されたり面倒なことを要求されたくないと思っている。
学校の先生にしてみたら専門家にああしなさい。こうしなさいって指図されるのって鬱陶しいと考えると思います。
まとめ

この本に書いてあることを学校の先生が実践してくれれば確実に話せるようになるとは言いませんが、良い影響を与えると思います。
ただしこの本を渡して「本に書いてあることを実践してください」と言ってもほとんどの先生は実践してくれないと思います。
実践するとなると手間がかかりすぎるんですよね。
あと学校の先生の能力や人間性に左右されてしまいます。
でも必ずしも教師を巻き込まなくてもできることはあります。
「場所」「人」「活動」の3つの組み合わせを考えて学校の先生と関係なくスモールステップをするのは有効ですし、全部実践するのは不可能ですが8割くらいの先生は負担のない範囲内なら実践してくれる人もいると思います。